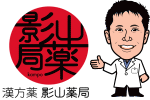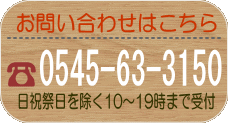過敏性腸症候群IBS
増え続ける過敏性腸症候群(IBS)
腹痛と便通異常を主体とする消化器症状が続くが、その原因として身体的な検査をしても器質的な異常がなく、機能面での異常だけが認められる病気です。
症状は腹痛、腹部膨満感、腹鳴、腹部不快感、ガスなど中心で、タイプとして下痢型・便秘型・下痢便秘交替型などのタイプ分類があります。
診断基準
ローマⅢより
6か月以上前から症状があり、過去3か月間は「月に3日以上にわたって腹痛や腹部不快感が繰り返しおこり、次の項目の2つ以上がある」
①排便によって症状が軽減する
②発症時に排便頻度の変化がある
③発症時に便形状の変化がある
症状は腹痛、腹部膨満感、腹鳴、腹部不快感、ガスなど中心で、タイプとして下痢型・便秘型・下痢便秘交替型などのタイプ分類があります。
診断基準
ローマⅢより
6か月以上前から症状があり、過去3か月間は「月に3日以上にわたって腹痛や腹部不快感が繰り返しおこり、次の項目の2つ以上がある」
①排便によって症状が軽減する
②発症時に排便頻度の変化がある
③発症時に便形状の変化がある

原因はストレス?
原因はストレスとの関係が強いことが示唆されていますが、原因がこれと決めつけられるものが無いのが現状です。
脳腸相関
脳と腸は神経でつながっており、親密な関係があります。(腸管神経叢)
脳がストレスを感じると,その刺激が腸管神経叢につながり,腸の運動や知覚などが敏感に反応します。そして腸管が反応すると、今度はその刺激が逆ルートで脳に伝わります。
これを脳腸相関と呼びます。
ストレスの刺激が腸管に伝わって下痢や便秘、腹痛などが起こると、今度はそれらの症状が脳にストレスを与えてしまうことがあり、IBSの患者は、脳腸相関が敏感になり、悪循環を起こしているのではないかと考えられています。(一説)
脳腸相関
脳と腸は神経でつながっており、親密な関係があります。(腸管神経叢)
脳がストレスを感じると,その刺激が腸管神経叢につながり,腸の運動や知覚などが敏感に反応します。そして腸管が反応すると、今度はその刺激が逆ルートで脳に伝わります。
これを脳腸相関と呼びます。
ストレスの刺激が腸管に伝わって下痢や便秘、腹痛などが起こると、今度はそれらの症状が脳にストレスを与えてしまうことがあり、IBSの患者は、脳腸相関が敏感になり、悪循環を起こしているのではないかと考えられています。(一説)
IBS,こんな人は要注意!
性格や生活環境との関連が示唆されています。
几帳面で神経質、ストレスが発散できないタイプ、時間に追われている、環境変化に適応できない、対人関係が複雑などと関連がある様です。真面目でナイーブな方、責任感が強く頼りがいのある人、頑張っている人(頑張り過ぎ?)などに多くみられるようです。
間違えやすい病気
乳糖不耐症
潰瘍性大腸炎
クローン病
憩室炎
大腸ポリープ、大腸がん
甲状腺機能亢進症、突発性膵炎、糖尿病、子宮内膜症など
几帳面で神経質、ストレスが発散できないタイプ、時間に追われている、環境変化に適応できない、対人関係が複雑などと関連がある様です。真面目でナイーブな方、責任感が強く頼りがいのある人、頑張っている人(頑張り過ぎ?)などに多くみられるようです。
間違えやすい病気
乳糖不耐症
潰瘍性大腸炎
クローン病
憩室炎
大腸ポリープ、大腸がん
甲状腺機能亢進症、突発性膵炎、糖尿病、子宮内膜症など
漢方薬で過敏性腸症候群を治す
具体的な排便異常があれば、先ずはその症状を中心に適応する処方が応じます。
症状の改善につれて脳腸相関の過敏性が取れてきますが、再発をしやすいのは生活環境やストレス、ホルモンバランスの乱れなどと関連が深いからです。
乱れがちな食習慣や生活スタイル、運動やストレス解消の不足、交感神経の亢進や冷えがあるなど、改善できるポイントを漢方薬を服用しながら整えていきます。

タイプ分類は以下になります。
症状の改善につれて脳腸相関の過敏性が取れてきますが、再発をしやすいのは生活環境やストレス、ホルモンバランスの乱れなどと関連が深いからです。
乱れがちな食習慣や生活スタイル、運動やストレス解消の不足、交感神経の亢進や冷えがあるなど、改善できるポイントを漢方薬を服用しながら整えていきます。

タイプ分類は以下になります。
| ①便秘型 | 排便回数や便の硬さだけでなく、左下腹部に残便感や膨満感を訴え、時に腹痛を伴います。痛みは痙攣性で潮の満ち引きのように繰り返しやすいです。ガスや排便後にはお腹の張りは楽になります。四逆散を中心に理気薬や柴胡剤が応じます。肛門のうっ血や肌荒れ、のぼせなどを伴えば、悪化や予防に駆お血薬を配します。 |
| ②便秘下痢タイプ | 便秘と下痢を繰り返すこのタイプは、大黄やセンナなどを安易に使うことが出来ません。暫く排便が無いと思ったら急に腹痛や下痢を起こします。ストレスからの影響が大きく、症状に規則性がありません。腸内の水分代謝を改善する利水薬を中心に、柴胡剤、理気剤がこれに応じます。 |
| ③下痢タイプ | 水溶性の下痢を繰り返し、一日に何度もトイレに行く事もしばしばあります。エネルギーを作り出す胃腸が弱いタイプですから、補気薬と呼ばれる人参製剤を中心に、利水薬が応じます。 内臓下垂タイプで太れない、体力が落ちているなど脾虚とよばれるタイプなため、再発しやすいのが特徴です。腹痛を伴うなら芍薬甘草湯、下痢が続けば人参湯などが応じます。 脂っこいものなど食事内容に呼応する場合は、消化薬など胃の働きから整える処方が対応します。 |
| ④ガスタイプ | 放屁が多く、社会生活をする上でそのことが過度のプレッシャーになっています。腸内細菌叢のバランスを整える処方が応じますが、冷えを伴ったり、自律神経系の亢進がみられる場合があるなど複雑な様相です。 基本は理気剤が応じますが、排便異常を伴わないタイプと、便秘下痢などがあるタイプがあり、体質鑑別の上、細やかな対応が必要です。 |
体は飲食物として取り込んだものを利用し、不必要なものを大小便や汗、髪の毛、爪、皮膚、月経血などから排泄します。東洋医学ではこれらの出口を本来あるべき形に再調整する治療法ですから、具体的な症状をとってからは再燃や慢性化を防ぐ手段を考えます。
気の巡りが失調した気滞と呼ばれる状態がベースにあり、その失調がどのように派生していくかによって薬剤は変わります。しかしこれは結果に対するアプローチの一端に過ぎません。生活環境を整えたり運動を取り入れたりすることで症状が改善する例もあります。
そうやって少しずつ余裕度が増してくると、原因の本丸にアプローチできるようになってきます。(例えば社会や自己との不協和、病気に対する考えなど)
生活環境からの影響が大きいと言われる過敏性腸症候群のような症状は、症状をとりながら少しずつ余裕度を拡大していく事で、寛解していくものだと思います。
お気軽にご相談ください。
shop info店舗情報
漢方薬 影山薬局
〒416-0909
富士市松岡486‐4
TEL.0545-63-3150
FAX.0545-63-6127
駐車場有り
営業10:00~18:30
(日祝祭日除く)